| エフェソス博物館 |
|
|
 エフェソス遺跡の近くの「エフェソス博物館」に行きました。 エフェソス遺跡の近くの「エフェソス博物館」に行きました。
エフェソス遺跡からの発掘品を展示しています。遺跡にある物はコピーでこちらに本物があったりします。
| |
|

| |
|
 見事は彫刻です。紀元前の物が見事に残っていることにも驚かされます。 見事は彫刻です。紀元前の物が見事に残っていることにも驚かされます。
| |
|
 とてもリアルな少年の顔。 とてもリアルな少年の顔。
| |
|
 紀元2世紀頃のアルテミス像 紀元2世紀頃のアルテミス像
更にもう一体アルテミス像が有りました。
| |
|
2023年4月1日(土)11:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| エフェソス その2 |
|
|
 クレティア通りは両側に位置する屋根付きで支柱のあるモザイクで覆われたギャラリーに向かって、商店や家々、その他の建物の扉が開かれていました。 クレティア通りは両側に位置する屋根付きで支柱のあるモザイクで覆われたギャラリーに向かって、商店や家々、その他の建物の扉が開かれていました。
| |
|
 クレティア通りを下っていくと右手に見えてくるのがトラヤヌスの泉。皇帝トラヤヌスに捧げられた泉です。 クレティア通りを下っていくと右手に見えてくるのがトラヤヌスの泉。皇帝トラヤヌスに捧げられた泉です。
| |
|
 エフェソス遺跡のシンボルになっている図書館の門です。 エフェソス遺跡のシンボルになっている図書館の門です。
| |
|
 素晴らしい彫像が残っています。 素晴らしい彫像が残っています。
目を見張るほどの美しさです。
| |
|
 この大劇場には24000人入ります。 この大劇場には24000人入ります。
音響効果が良く演劇や集会や演説が行われました。
この他アルテミス神殿跡も見ましたが、ローマ時代に再建されたものです。現在は1本のイオニア式の巨大な石柱だけが残されています。広々としていて当時の建物の大きさが偲ばれました。
| |
|
2023年4月1日(土)10:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| エフェソス |
|
|
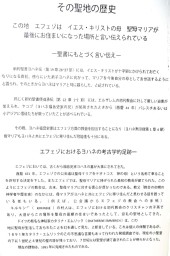 今日はエフェソス遺跡です。紀元前6千年前の新石器時代には周辺に人が住んでい、ヒッタイト、ギリシャ、後にローマの支配となります。 今日はエフェソス遺跡です。紀元前6千年前の新石器時代には周辺に人が住んでい、ヒッタイト、ギリシャ、後にローマの支配となります。
現在残るアルテミス神殿の遺構はローマ時代に建てられたもので、巨大な図書館と劇場を備えていました。
始めは聖母マリアの家です。
珍しく日本語の説明看板もありました。
| |
|
 イエスの母マリアも使徒ヨハネとともにエフェソスで余生を送ったと伝えられる小さな建物で聖母マリアの教会(審議会の教会)になっています。 イエスの母マリアも使徒ヨハネとともにエフェソスで余生を送ったと伝えられる小さな建物で聖母マリアの教会(審議会の教会)になっています。
| |
|
 ヴァリウスの浴場です。2世紀に造られた豪華なローマ浴場跡で、冷水浴、温水浴、マッサージ室、脱衣場、トイレなどがあります。 ヴァリウスの浴場です。2世紀に造られた豪華なローマ浴場跡で、冷水浴、温水浴、マッサージ室、脱衣場、トイレなどがあります。
| |
|
 音楽堂・オデオン 音楽堂・オデオン
この音楽堂は、収容人数1400人で、当時は上部に屋根がつけられていました。コンサートの他、会議にも使われました。
| |
|
 両側がイオニア式、真ん中がコリント式の柱です。また単純なドリス式の柱も見られました。 両側がイオニア式、真ん中がコリント式の柱です。また単純なドリス式の柱も見られました。
新しく建物を建てるとき、古い建物を壊してその石材を使っていました。また地震で壊れると再建しています。そのため色々な様式が混ざったりしているようです。
| |
|
2023年4月1日(土)09:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| カッパドキアを離れクサダシへ |
|
|
 今日は移動日です。 今日は移動日です。
カッパドキアを離れネブシェヒル空港からイスタンブール空港、乗り継いでイズミールへ向かいました。
イズミールから少し南下し、クサダシのホテルに到着です。
| |
|
 「カリスマ デラックスホテル」はその名の通りややキラキラ系ですが豪華なホテルです。岩ばっかりのカッパドキアからいきなり海のある風景となりました。 「カリスマ デラックスホテル」はその名の通りややキラキラ系ですが豪華なホテルです。岩ばっかりのカッパドキアからいきなり海のある風景となりました。
| |
|
 エーゲ海に面しプライベートビーチのようになっています。 エーゲ海に面しプライベートビーチのようになっています。
向かいはギリシャです。
| |
|
 今まで天候に恵まれず、今日のサンセットの時間は本当に綺麗でした。 今まで天候に恵まれず、今日のサンセットの時間は本当に綺麗でした。
| |
|
 プールサイドの部屋で、夜の海を見ながらの食事でした。 プールサイドの部屋で、夜の海を見ながらの食事でした。
| |
|
2023年3月31日(金)20:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| らくだ岩 |
|
|
 デヴレントの谷は、カッパドキア観光の拠点となるギョレメから北西に10kmほどの位置にあります。 デヴレントの谷は、カッパドキア観光の拠点となるギョレメから北西に10kmほどの位置にあります。
らくだ岩は、トルコ・カッパドキアのデヴレントの谷にある有名な奇岩の一つです。
| |
|
 雪がおおくて遠景が見えません。 雪がおおくて遠景が見えません。
| |
|
 昼食は雰囲気のある良い店でした。店の前にもカッパドキアの雰囲気があります。 昼食は雰囲気のある良い店でした。店の前にもカッパドキアの雰囲気があります。
トルコ料理にもちょっと飽きてきました。提供される料理は日本人だから少なめにと言ってあるそうですが、食べきれない量です。
トルコの人はガタイが良く、非常に沢山食べるようです。
| |
|
 谷が赤く見える「ローズバレー」です。夕陽の時に見るのが最高だそうです。 谷が赤く見える「ローズバレー」です。夕陽の時に見るのが最高だそうです。
雪のせいでそれ程赤く見えません。
| |
|
 すぐ傍の案内人の知り合いの家を訪問。 すぐ傍の案内人の知り合いの家を訪問。
洞窟の家です。家中絨毯を引き詰め織物やら編み物を手仕事でしていて少し販売していました。
とても素朴な感じを受けました。
| |
|
2023年3月30日(木)13:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| ギョレメ野外博物館 |
|
|
 カッパドキアの中でも最大の奇岩がある所です。 カッパドキアの中でも最大の奇岩がある所です。
中は広大で信じられない形の奇岩が一杯です。
| |
|
 向きが変ですがクリックすると普通に見られます。 向きが変ですがクリックすると普通に見られます。
| |
|
 近くで見ると凄い迫力です。 近くで見ると凄い迫力です。
中へ入れるところも充分部屋とし使える広さです。
| |
|
 浸食されてこうなったことは解りますが、実際に見ると自然の妙を感じます。 浸食されてこうなったことは解りますが、実際に見ると自然の妙を感じます。
| |
|
 茸のような不思議な形で、ちょうど屋根のように見えます。 茸のような不思議な形で、ちょうど屋根のように見えます。
| |
|
2023年3月30日(木)09:19 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| ウチヒサル |
|
|
 ウチヒサルはカッパドキアの最高所にあり素晴らしい景観が望めます。ウチヒサルは、ギョレメのすぐ近くです。 ウチヒサルはカッパドキアの最高所にあり素晴らしい景観が望めます。ウチヒサルは、ギョレメのすぐ近くです。
あいにくの雪で登ることも出来ませんでしたが雰囲気だけは味わえました。
| |
|
 ウチヒサルの頂点にある「ウチヒサル城塞」は、古代ローマ時代後期、ギリシャ人のキリスト教徒がローマ帝国の迫害から逃れるためにこの地に隠れ住んだことが始まりと言われています。 ウチヒサルの頂点にある「ウチヒサル城塞」は、古代ローマ時代後期、ギリシャ人のキリスト教徒がローマ帝国の迫害から逃れるためにこの地に隠れ住んだことが始まりと言われています。
数々の争いの中で、この巨大な岩山は城壁の役割を果たしてきました。
写真では見られませんが、実際に要塞のようになっています。
| |
|
 三美人はカッパドキアにある最も有名な奇岩の一つです。 三美人はカッパドキアにある最も有名な奇岩の一つです。
帽子を被ったような背の高いキノコ岩が3つ並んでいる姿から、三美人の岩と呼ばれています。
| |
|
 MDC ケーブ ホテルに到着、ウルギュップ旧市街の歴史的建物内にある豪華な洞窟ホテルで、渓谷のパノラマの景色を望めます。 MDC ケーブ ホテルに到着、ウルギュップ旧市街の歴史的建物内にある豪華な洞窟ホテルで、渓谷のパノラマの景色を望めます。
| |
|
 客室は、床暖房付きの大理石フロアで、アーチ型の天井、石の暖炉が特徴です。 客室は、床暖房付きの大理石フロアで、アーチ型の天井、石の暖炉が特徴です。
寒くて床暖房は快適でした。
荷物を減らすため途中でクリーニングをするつもりでした。此処に2泊するため早速クリーニング。
| |
|
2023年3月29日(水)16:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| カイマクルの地下都市 |
|
|
 アンカラから約300km、3時間30分程でカッパドキアです。バスにはWiFiもあり快適でした。 アンカラから約300km、3時間30分程でカッパドキアです。バスにはWiFiもあり快適でした。
カッパドキアの街は大きく4つに分かれていて、中心が観光客でにぎわう「ギョレメ」、遠方からのバス発着や空港のある西の「ネヴシェヒル」、東の「ウルギュップ(ユルギュップ)」、川のほとりにある静かな北の「アヴァノス」となっています。
ギョレメの南「カイマクルの地下都市」へ向かいました。
石灰岩を掘って地下8階から10階の深さにまで達している巨大な地下都市です。
| |
|
 完全に地下部分に作られていることとその規模の大きさから、他のカッパドキアの岩窟住居とは違います。カッパドキアは地下都市の街でもあります。 完全に地下部分に作られていることとその規模の大きさから、他のカッパドキアの岩窟住居とは違います。カッパドキアは地下都市の街でもあります。
地下都市での生活はキリスト教時代以前からすで営まれていましたようですが、一時は頻繁に利用されたのはアラブ人から逃れるキリスト教徒の避難所にもなりました。
この穴の空いた石は敵の侵入を防ぐための石です。敵も侵入しようとして穴を開けましたが、一人しか作業できないため諦めた名残です。
ダイナマイトでも無い限り進入は不可能です。
| |
|
 内部は、狭い通路から生活の場、換気孔までと様々な空間があり、まるで迷路になっています。 内部は、狭い通路から生活の場、換気孔までと様々な空間があり、まるで迷路になっています。
| |
|
 「ギョレメ」に到着し高台のレストランで食事となりました。 「ギョレメ」に到着し高台のレストランで食事となりました。
| |
|
 見晴らしが良くて、眼下に外で寝るようなホテルも見られました。 見晴らしが良くて、眼下に外で寝るようなホテルも見られました。
この景色がカッパドキアを象徴する風景です。
日本なら草木が生えそうですが、石灰岩で水はけが良く乾燥しているので岩のままです。
| |
|
2023年3月29日(水)12:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| アタテュルク廟 |
|
|
 昼食が終わり「アタテュルク廟」です。アタテュルク廟はトルコ共和国の首都アンカラにある、初代大統領ムスタファ・ケマル・アタテュルクの霊廟です。 昼食が終わり「アタテュルク廟」です。アタテュルク廟はトルコ共和国の首都アンカラにある、初代大統領ムスタファ・ケマル・アタテュルクの霊廟です。
トルコ独立戦争とトルコ革命を僚友たちとともに指導してトルコ共和国を樹立。宗教(イスラム教)と政治を分離しなければトルコ共和国の発展はないと考え、新国家の根幹原理として政教分離(世俗主義)を断行。憲法からイスラム教を国教とする条文を削除しました。
トルコ語表記をアラビア文字からラテンアルファベットへ変更、一夫多妻禁止や女性参政権導入、スルタン制を廃止などトルコの近代化を推進しました。
教育制度も確立し、刑務所でも読み書きを教え。読み書きができるようになると釈放と凄い政策です。
トルコ大国民議会から「父なるトルコ人」を意味する「アタテュルク」の称号を贈られました。現代トルコの国父でガイドさんもとても尊敬しているようで、話しぶりからも思い入れが伺えました。
| |
|
 中は大変綺麗で荘厳な感じでした。 中は大変綺麗で荘厳な感じでした。
| |
|
 周りは博物館になっていて、トルコ独立戦争とトルコ革命の様子や、アタチュルクの使った車などが展示されていました。 周りは博物館になっていて、トルコ独立戦争とトルコ革命の様子や、アタチュルクの使った車などが展示されていました。
| |
|
 この廟は軍が管理していて、衛兵の交代が行われます。 この廟は軍が管理していて、衛兵の交代が行われます。
| |
|
 宿泊のアンカラ・ヒルトンはなかなか良いホテルでした。 宿泊のアンカラ・ヒルトンはなかなか良いホテルでした。
| |
|
2023年3月28日(火)14:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| アナトリア文明博物館 |
|
|
 トルコの首都アンカラの「アナトリア文明博物館」に到着。古代文明の遺物を展示している博物館で、トルコに存在した様々な文明の歴史、文化、美術などが見られました。 トルコの首都アンカラの「アナトリア文明博物館」に到着。古代文明の遺物を展示している博物館で、トルコに存在した様々な文明の歴史、文化、美術などが見られました。
長い歴史があるトルコでは、旧石器時代からビザンツ帝国時代までの遺物が展示されています。
| |
|
 エジプトのラムセス2世の王妃ネフェルタリから、ヒッタイトのハットゥシリ3世の王妃プドゥヘパに送られた楔形文字で書かれた友好の粘土板は、最も重要な展示物の一つです。 エジプトのラムセス2世の王妃ネフェルタリから、ヒッタイトのハットゥシリ3世の王妃プドゥヘパに送られた楔形文字で書かれた友好の粘土板は、最も重要な展示物の一つです。
| |
|
 人類で初めて鉄を利用したヒッタイト時代のコレクション。 人類で初めて鉄を利用したヒッタイト時代のコレクション。
あまりにも長い歴史があるので混乱します。
| |
|
 アナトリア文明博物館はアンカラ城の中腹にあるので、アンカラの街が一望できます。 アナトリア文明博物館はアンカラ城の中腹にあるので、アンカラの街が一望できます。
| |
|
 昼食のレストランはラマダンの最中なので、我々旅行者以外は全く人が居なくて閑散としていました。 昼食のレストランはラマダンの最中なので、我々旅行者以外は全く人が居なくて閑散としていました。
トルコ美人の給仕の女性!
| |
|
2023年3月28日(火)12:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| 羽田からアンカラへ |
|
|
 いよいよトルコ旅行の始まりです。21時55分羽田発と遅い時間なのでノンビリと出かけました。 いよいよトルコ旅行の始まりです。21時55分羽田発と遅い時間なのでノンビリと出かけました。
京急を降りると突然スーツケースが動かなくなりました。少し音が大きいと思っていたのですが車輪が木っ端みじんになっていました。修理する所は第3ターミナルには無いとのことです。古くなってもいたので仕方なく購入することにしました。サムソナイトの店しか無くて、きっちり定価で購入しました。
スタートから不吉な予感。
搭乗手続きになり席の電動リクライニングが動かないと言われました。キャビンアテンドに言えばその都度手動で動かせるとのことでした。満席でどうにもならないとのことでした。呼ぶと女性キャビンアテンドでは動かせなくて、男性のアテンダントがギコギコやって動かせる有様。何度も呼ぶのは気が引けるし大変でした。
| |
|
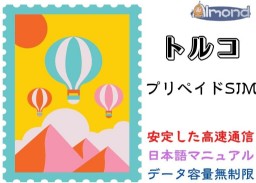 トルコは電波事情が良く空港でSimを買いたいと思っていたのですが、添乗員からイスタンブール着が現地時間5時なので購入出来ないと言われ、日本で10日間2480円のプリペイドSimを買って行きました。 トルコは電波事情が良く空港でSimを買いたいと思っていたのですが、添乗員からイスタンブール着が現地時間5時なので購入出来ないと言われ、日本で10日間2480円のプリペイドSimを買って行きました。
実際には空港は24時間営業で「Vodafon」 「TURKCELL」 「TURK TELEKOM」全ての店が開いていました。添乗員はベテランでしたが、スマホ関係には弱くて情報不足でした。
けれど日本から持ち込んだSimが無事作動し一安心。
イスタンブールからアンカラへ乗り継いで28日9時過ぎに到着
| |
|
2023年3月27日(月)23:59 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| チューリップまつり |
|
|
 天気が良いので吉田公園に行きました。 天気が良いので吉田公園に行きました。
桜は未だでしたが「チューリップまつり」でした。
入り口の池はとても綺麗で、そろそろ桜が咲き始めていました。
| |
|
 とても暖かく、滝の周りの柳は初夏の装いでした。 とても暖かく、滝の周りの柳は初夏の装いでした。
| |
|
 チューリップ畑にとても小さな兄弟。 チューリップ畑にとても小さな兄弟。
癒やされるショットです。
| |
|
 どれも同じように見えますが、実は色々な種類のチューリップなのです。 どれも同じように見えますが、実は色々な種類のチューリップなのです。
| |
|
 少し歩くと汗ばむ程の陽気でした。 少し歩くと汗ばむ程の陽気でした。
| |
|
2023年3月24日(金)16:31 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| 溝口好晴「心に響く和の万華鏡展」 |
|
 |
|
今日から葛城北の丸2階ギャラリーにて開催されると聞き、早速訪問しました。
https://www.yamaharesort.co.jp/katsuragi-kitanomaru/info/011.php
長く来ていなかったのですが、堂々たる作りです。
| |
|
 午後からレストランが休みのためか、ひっそりとしていました。 午後からレストランが休みのためか、ひっそりとしていました。
| |
|
 中は木造で庭が大変綺麗です。 中は木造で庭が大変綺麗です。
| |
|
 庭はとても広くて、奥の葛城ゴルフ場も沢山あるこの辺りでは随一のゴルフ場です。 庭はとても広くて、奥の葛城ゴルフ場も沢山あるこの辺りでは随一のゴルフ場です。
| |
|
 万華鏡が展示されていました。 万華鏡が展示されていました。
建物とよくマッチしていて素晴らしい感じでした。
| |
|
2023年3月13日(月)19:57 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| 龍尾神社 |
|
|
 掛川市では由緒ある神社で、庭園のしだれ梅は有名です。 掛川市では由緒ある神社で、庭園のしだれ梅は有名です。
神社隣接の庭園に咲き誇る約300本の「しだれ梅」です。
入り口には駐車場の整理の人達、ちょっとした店も出ていて賑わっていました。
| |
|
 かつて婦人はお気に入りの着物を身にまとい、その香が衣にうつるように、ゆったりと梅の花見を楽しんだと云われます。 かつて婦人はお気に入りの着物を身にまとい、その香が衣にうつるように、ゆったりと梅の花見を楽しんだと云われます。
マスクをしているのと、今日は風が強く、花粉症でも有り香りは今一つでした。
| |
|
 開花は八分程度でした。 開花は八分程度でした。
| |
|
 すべてが枝垂れ梅で非常に揃っていました。 すべてが枝垂れ梅で非常に揃っていました。
| |
|
 場所によっては満開の梅が見られました。 場所によっては満開の梅が見られました。
| |
|
2023年3月2日(木)18:35 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| 福田沢 |
|
|
 早咲きの河津桜が咲いていると聞き「福田沢」に行ってみました。 早咲きの河津桜が咲いていると聞き「福田沢」に行ってみました。
場所が解りにくくて苦労しましたが、案内看板が出ていてなんとかたどり着けました。
| |
|
 到着した時間が遅く日陰になっていましたが、桜並木を見られました。 到着した時間が遅く日陰になっていましたが、桜並木を見られました。
今日は空は雲一つ無くて暖かく、春の陽気でした。
| |
|
2023年2月27日(月)18:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| 友人と |
|
|
 先日気に入った場末のスナックで友人と飲みました。 先日気に入った場末のスナックで友人と飲みました。
今宵は友人もすっかりリラックスして沢山歌いました。コロナ禍で歌っていなかったので、歌えると盛り上がります。
面白くてあっという間に時間が経ちました。
| |
|
2023年2月25日(土)23:59 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| マッターホルン |
|
|
 スイスにスキーに行っている友人から写真が送られてきました。ツェルマット(Zermatt)ズンネッガ(Sunnegga)だそうです。 スイスにスキーに行っている友人から写真が送られてきました。ツェルマット(Zermatt)ズンネッガ(Sunnegga)だそうです。
| |
|
 天気が良くてマッターホルンが綺麗に写っています。 天気が良くてマッターホルンが綺麗に写っています。
| |
|
 マッターホルンは神々しくさえ見えます。 マッターホルンは神々しくさえ見えます。
スキーをしないので同行しませんでしたが、景色だけでも見たいと思いました。
| |
|
2023年2月22日(水)22:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| 黒田家代官屋敷 |
|
|
 黒田家代官屋敷は、遠江国城東郡嶺田(現・静岡県菊川市下平川)にあった代官屋敷です。 黒田家代官屋敷は、遠江国城東郡嶺田(現・静岡県菊川市下平川)にあった代官屋敷です。
詳細はこの案内板にあります。
梅まつりの期間なので無料で入場できました。
| |
|
 長屋門は桁行20.6メートル、梁間4.7メートルの長大な門で、東寄りに出入口を設け、その左右は部屋や蔵とする。主屋より古い18世紀半ばの建築だそうです。 長屋門は桁行20.6メートル、梁間4.7メートルの長大な門で、東寄りに出入口を設け、その左右は部屋や蔵とする。主屋より古い18世紀半ばの建築だそうです。
| |
|
 米蔵と東蔵は主屋と同じ19世紀半ばの建築です。 米蔵と東蔵は主屋と同じ19世紀半ばの建築です。
前庭が広々しています。
| |
|
 裏庭が広くて東蔵と西蔵があり梅の木が沢山有りました。 裏庭が広くて東蔵と西蔵があり梅の木が沢山有りました。
未だ早すぎて白梅は6分咲き程度でしたが、紅梅は殆ど蕾みでした。
| |
|
 黒田家代官屋敷資料館を見ようとしたら、カメラを持っているだけなのに 黒田家代官屋敷資料館を見ようとしたら、カメラを持っているだけなのに
「写真撮影禁止で・・・」と受付の変なお爺さんが叫ぶので入り口から覗いただけとなりまし。
ボランティアの方かもしれませんが、張り切りすぎで違和感がありました。
| |
|
2023年2月17日(金)16:44 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| 夕焼け |
|
 |
|
夕方走っていたら空が真っ赤でした。いつの間にか日が長くなったと気がつきました。
でも明日は天気が崩れて東京でも雪が降りそうだとか、静岡県西部でも雪が降るかもしれません。
殆ど降らない地区なので、雪が降ったら嬉しいな!
| |
|
2023年2月9日(木)17:45 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|
| 小樽、支笏湖氷瀑祭り |
|
|
 旅行も最後の日となり札幌から小樽に向かいました。雪は積もっていますが、天気は良く散策しました。 旅行も最後の日となり札幌から小樽に向かいました。雪は積もっていますが、天気は良く散策しました。
小樽では船の硝子製浮きを作っていた伝統からガラス店
が沢山あります。またオルゴールも沢山売られています。
大きなガラス店「北一硝子」から散策開始。
| |
|
 船乗り場は日曜日とあって、人で溢れかえっていました。 船乗り場は日曜日とあって、人で溢れかえっていました。
| |
|
 この写真の左側運河沿いの「ホテルソニア」で昼食でした。寿司セットでしたがネタ新鮮で満足しました。 この写真の左側運河沿いの「ホテルソニア」で昼食でした。寿司セットでしたがネタ新鮮で満足しました。
好天ながら雪が残り綺麗な写真になりました。
| |
|
 小樽から支笏湖に向かい「支笏湖氷瀑祭り」を見学。 小樽から支笏湖に向かい「支笏湖氷瀑祭り」を見学。
スプリンクラーで水を掛け続け塔や山を作った物です。
飛行場にも近く、時間的な関係で沢山のバスが来ていました。
| |
|
 札幌雪まつりと違い、かなり自然に造形されていて面白いと思いました。 札幌雪まつりと違い、かなり自然に造形されていて面白いと思いました。
支笏湖から新千歳空港へ向かい羽田。飛行機は満席でした。搭乗手続きも一杯で遅れて出発でしたがほぼ定刻通りに羽田に到着でした。
| |
|
2023年2月5日(日)14:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理
|